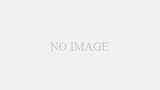要点(先に3行)
- 新人が辞める原因のひとつは「何をどこまでできればいいのか分からない」こと。
- OJTチェックリストで学習の到達点を明確にすれば、不安が減り、成長が見える。
- 教える側にとっても「育成のばらつき」がなくなり、チーム全体の安心感につながる。
「そろそろ一人でできるよね?」
新人にそう声をかけたら、不安そうな顔をされた…。
そんな経験はありませんか?
実は、新人が一番つらいのは「自分がどこまでできれば合格なのか分からないこと」です。
一方で先輩は「このくらいはもうできて当然」と思っている。
このギャップが新人を追い詰め、早期離職の原因になってしまいます。
なぜチェックリストが必要なのか?
薬局の教育は、多くがOJT(仕事をしながら学ぶスタイル)です。
でも、OJTは放っておくと 「教える人によって基準がバラバラ」 になります。
- A店舗では「2週間で調剤室に一人立ち」
- B店舗では「3か月は必ず先輩と一緒」
同じ会社でも店舗によって全く違う基準になってしまう。
新人からすれば「私は遅れているのか?」「できていないのか?」と不安を抱えやすくなりますよね。
だからこそ、OJTチェックリストで“できるライン”を見える化することが必要です。
OJTチェックリストに入れるべき項目
薬局の現場に合わせてカスタマイズできますが、概ねこのような項目が入っているとよいですね。
1. 業務スキル
- 受付対応(患者さんへの声かけ、処方箋の確認)
- 調剤補助(ピッキング、鑑査補助)
- 投薬補助(薬歴確認、服薬指導補助)
- レセプト処理(入力、点検)
2. 行動スキル
- あいさつ・笑顔・声の大きさ
- 患者さんやスタッフへの報告・連絡・相談
- ミスをした時の報告態度
3. マインド・姿勢
- 分からないことを質問できるか
- 新しいことに挑戦する意欲
- チームで協力できる姿勢
👉 これらを「できた/できない」でチェックするだけでも、新人はゴールをイメージしやすくなります。
導入するとどう変わる?
チェックリストを使うと、こんな変化が起こります。
- 新人にとって:「合格ライン」が分かるので安心できる。成長が目に見える。
- 教える側にとって:何をどこまで教えたかが共有できる。教育のばらつきがなくなる。
- 経営者にとって:育成の進捗を把握でき、属人的にならない仕組みをつくれる。
まとめ
新人が辞める理由のひとつは「できるようになった基準が不明確」だから。
その不安をなくすのが、OJTチェックリストです。
「どこまでできたら一人前か」を言葉にするだけで、
新人は安心し、先輩は教えやすくなり、経営者は状況を把握できます。
あなたの薬局でも、まずは「この業務ができたらOK」というリストを作ってみませんか?
定着は偶然ではなく、基準を共有する仕組みで設計できるのです。